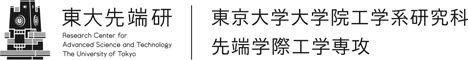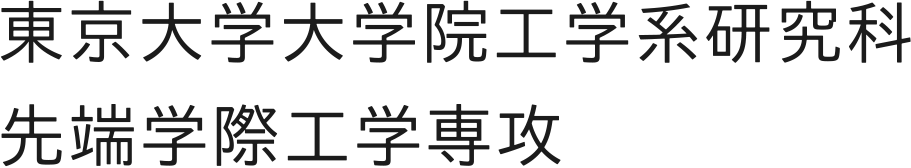小川 奈美さん(廣瀬・葛岡・鳴海研究室)

-
東京大学大学院学際情報学府学際情報学専攻を経て、2017年4月東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士後期課程(廣瀬・谷川・鳴海研究室:当時)入学。2017年10月からNTTコミュニケーション科学基礎研究所人間情報研究部・感覚表現グループにてインターンを、2018年1~6月にはフランスINRIAにて客員研究員を経験。
VR(バーチャル・リアリティ)技術は、あたかも実際とは異なる空間にいるかのような錯覚を生み出すことができます。ところが、実は空間だけでなく、自分の身体をも自在に変えることができます。しかし、自分の身体が変わることで世界の認識の仕方にどのような影響があるのかは、これまでほとんど明らかにされていませんでした。 そこで、バーチャル空間で自分の代替となる「自己アバター」を使い、アバターの見た目が変化したときにユーザーが空間をどのように感じるか、どのように振る舞うようになるかという知覚や行動への影響を、VRを使った心理実験で検討する研究を行ってきました。その結果、アバターの見た目が知覚や行動に影響を与えることが明らかになりました。この成果は、VRでのアバターの設計指針の策定に貢献します。
「自己とは何か?」を知りたかった
今の研究に進むきっかけは、神経科学者V.S.ラマチャンドランが書いた『脳のなかの幽霊』という本を学部生のときに読んだことでした。事故や手術などで手足を失った人が、失ったはずの部分に痛みを感じる「幻肢痛」の治療法として、鏡を用いた簡単な装置をラマチャンドランが考案するエピソードなどが描かれています。そこで、「自己とは何か?」という今の研究につながる興味を持ったと思います。
学部3年生で心理学を専修して知覚心理学を学びましたが、修士課程に進む2015年ごろにVRブームが起こっていたこともあり、VRを使った研究をしている廣瀬・谷川・鳴海研究室(当時)に入りました。
修士課程ではメディアアート展を開催する授業があり、私は、指の伸びたバーチャルな手でピアノを弾くことができる『えくす手』という装置を出展しました。実際にはあり得ない見た目の身体を使うことで、人はそれを自分の身体だと感じられるのかということを試したかったのです。
分野を跨いだ、自由な研究ができる土壌
このように、自分の興味を深掘りしようと思うと、分野を跨いだ研究が必要になります。つまり、心理学の観点から「リアリティをどう感じるのか?」を探るための研究と、工学的な観点から表現方法を模索して「どのようにバーチャルなリアリティを作り出すのか?」を追求するための研究です。
その意味で、博士課程に進むにあたり、学際的な先端学際工学専攻を選んだことは、私にとっては自然な選択でした。 例えば、先端学際工学専攻の特徴でもある「先導人材育成プログラム(I)」では、受講生が指導教員以外の異分野の教員を選び、プロポーザル(研究企画書)を作成します。私のプロポーザル教員は認知科学を専門とする渡邊克巳客員准教授(当時)で、そこで補いたかった心理学的な視点が得られたと思います。
思い返せば入試のときも、人間支援工学分野の中邑賢龍教授に福祉の視点からの質問を受けて、目を開かされたことがありました。異分野の視点から学ぶことは多いと実感します。
一見、遠回りだけれども一直線な道
先端学際工学専攻在学中には、心理学分野の専門家と研究をするためにNTT研究所でインターンをしたり、海外の研究環境を体験するためにフランスの研究機関で研究を行ったりと、そのときの問題意識に従ってさまざまな環境に自分の身を置くことができました。 所属する研究室が本郷にあったために駒場での必修科目への出席が大変でしたし、学会発表なども多く忙しい日々でしたが、自由で学際的な研究環境の中で存分に自分の興味と研究に突き進めたと思っています。
修士課程での『えくす手』は「人は見た目や機能の異なる身体をどこまで自分の身体と感じられるのか」がテーマでしたが、博士課程では「身体が変わったときに、人の世界の感じ方は変わるのだろうか」というテーマになりました。
心理学と工学の間を行ったり来たりし、途中で大学の外にも活動範囲を広げてきた私の道は、一見、遠回りのように感じるかもしれませんが、自身では一直線に進んできたつもりです。
「産」と「学」の連携を助ける架け橋になりたい
現在、IT系の企業に研究職として所属し、これまでの研究を続けています。 実は就職活動時にはその会社に研究職はなく、VRのサービスを取り扱う部署のポジションがあったので応募しました。面接時に、自分がどのような価値を提供できるかという話をしたところ、初めての研究職として採用され、結果的に新しくポジションを作った形になりました。
近年、産学連携が盛んですが、産業界とアカデミアの間では互いの求める方向が異なる場合があり、思うように連携が進まないことがあります。私は、「学」から「産」に研究の場を移すことで、その連携をすみやかにうながす架け橋役を果たしたいと思っています。それも私にとっては遠回りではなく、一直線の道です。