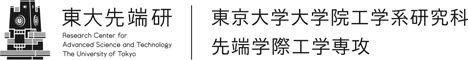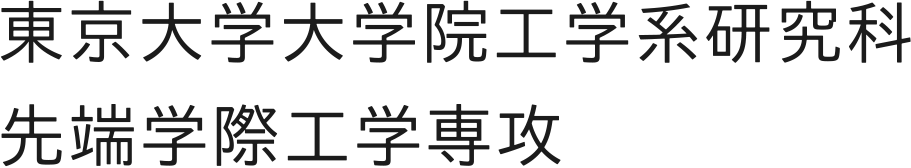- ホーム
- 専攻について
- 先端学際工学専攻 開設30周年
- 歴代専攻長より
歴代専攻長より

1995-1998年度
児玉 文雄
- 東京大学 名誉教授
先端学際工学専攻30周年に寄せて
私は、「科学技術政策」の講座に属し、1995年から1998年まで、専攻長を務めました。その専攻が、四半世紀を過ぎて、30年にも及ぶ歴史を刻んだことを、まず、お祝い申し上げます。私自身は、1964年に機械工学部を卒業し、その専攻で論文博士を取得して以来、一貫して科学技術政策に関連した研究に(国内および欧米で)従事して来ました。その間、多数の後輩たちと共同研究をしてきましたが、彼らが博士号まで到達するのは簡単ではありませんでした。しかも、この分野の博士論文を審査する部門が存在しなかった事実も、その困難さに拍車をかけていました。この困難さを一挙に打破したのが、先端学際工学専攻に設立された、「科学技術・社会相関」部門の設置でした。先端学際工学専攻の目的は、社会人に学位を与えることを大きな目的にしておりました。科学技術政策の分野において、学位論文を作り上げるには、社会経験が何より必要でした。以上のような複数の要因が重なって、この専攻課程に入学を志望する社会人が急増しました。その結果、2003年までの私の先端研での在任中に、二桁に及ぶ、博士号を生み出しました。彼らの多くは、出身の職場に一旦は戻りましたが、しばらくして、すべての卒業生が、国立・私立の大学に職を得て、研究教育で活躍しております。彼らの論文の多くは、日本の先端技術の国際競争力がピークに達していた時期の企業の技術開発を分析し、英文誌に発表したものでした。幸運にめぐり合わせたことも忘れてはなりませんが、分析手データの蓄積や、分析方法の充実により、この分野の研究で、日本が世界をリードすることを願うものです。
※平成7年4月1日より「工学系研究科の専攻長に関する内規」が施行された。当初、柳田博昭教授が専攻長となり、同年5月16日付けで児玉文雄教授が新たな専攻長となった。

1999, 2000, 2003-2006年度
堀 浩一
- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 理事
- 東京大学 名誉教授
先端学際工学専攻設立の頃を振り返って今思うこと
先端学際工学専攻が設立されたのは1992年だと思いますが、当時、私はまだ助教授でした。
大学院重点化の前の時代は、学部の教官(法人化前ですので教員ではなく教官でした)と附置研究所および学内共同利用センターの教官とが協力して大学院を運営するという形態でした。大学院重点化が実施されると、大学院に所属する大学院専任教官が学部の学科目を兼担するという形になることが予想され、そうなると、研究所やセンターの大学院における地位が低下してしまうのではないか、という危機感を研究所やセンターが抱くことになりました。他の研究所やセンターが地位の約束を求めるような動きをする中で、先端研の動きは異なっていました。今でもそうなのだろうと思いますが、先端研の教授会は、教授と助教授の分け隔てなく、常に明るく前向きに、根回しなしの本音の議論を行っていました。きわめて重大な問題ですから、当然のことながら激論が交わされましたが、あっという間に、「だったら、自分達で大学院を新しく作ってしまおう」という結論に到達しました。工学部、理学部、経済学部、教養学部などのさまざまな学部の教官が集まって先端研を構成していましたので、すべての学部を横断するような独立研究科を設立しよう、ということになりました。先端研はまだ附置研究所ですらなく学内共同利用センターでしたから、古い組織の皆様は、「何と馬鹿げた大胆なことを先端研は言い出したのだ」という感想を抱かれたことでしょう(実際、私も、そういう感想を直接聞かされました)。「しかし、単純に大学院を作りたいでは通らないね。今一番求められているのは、社会人の再教育を行う大学院じゃないかな。よし、それで行こう」という方針も、あっという間に決まりました。紆余曲折を経て、独立研究科は実現しなかったものの、工学系研究科の中に、先端学際工学専攻が設立されることになりました。
私は、1998年に先端学際工学専攻専任の教授となり、六たび、専攻長を務めることとなりました。普通の専攻の教員は、一度か二度、専攻長を務めるだけだと思いますので、専任講座の少ない独立専攻のつらさです。大学院重点化が実施されてからしばらくは、まだ運営体制が昔のままで、学科長会議と常務委員会があるだけで、専攻長の出番はそれほどなかったようですが、私が専攻長になった頃には、すでに専攻長の仕事の重みが増していて、専攻長会議への出席も求められました(が、学科長には手当が出ていたものの、専攻長手当は、まだ、ありませんでした(笑))。
各種の専攻長業務の中で、最も重い仕事は、1999年10月に実施した「外部評価」だったと思います。私の手元に、その報告書の原稿が残っています。今読むと、なかなか興味深いものがあります。自己評価の一部にはこんなことが書かれています。「専攻設立当初は、社会人教育に対する認識もまちまちであり、カルチャーセンターと勘違いした受験生なども見られ、教官、学生ともにいろいろと当惑する面もあったが、現在においては、先端学際工学専攻は社会人にも開かれた昼間フルタイムの博士課程として一定の形を示している。すなわち、社会人教育に期待される役割が、研究指導者養成、研究者養成、職業人育成、教養教育に大別されるとするならば、先端学際工学専攻は、研究指導者養成のための専攻としての役割を果たしているといえる。付録に示すとおり、先端学際工学専攻の卒業生は、各界で大活躍している。しかし、見方によっては、その活躍の場は、社会からの期待に比べると限定された世界であると言わざるをえないかもしれない。」それに対し、外部評価委員(民間企業役員など)からは、「従来型の大学でできなかったことに挑戦することは、きわめて重要である。1990年代に日本がアメリカに負けてしまったとするならば、それは、アメリカの多様性に負けたのであるといえる。今、日本の社会に求められているのは、多様性であり、大学においても、すべての大学が同じ方向を向くことは避けなければならない。それぞれの大学、それぞれの学部、それぞれの学科で特色を出す必要がある。その意味でも、日本の国立大学で、最初に社会人大学院に取り組んだ先端学際工学専攻の役割は、高く評価することができる。今後も新しい試みに積極的に取り組んでいただきたい。」と高く評価していただく一方、「博士の学位を取得したからといって、待遇が改善されることもない。研究所においては学位が必要であるが、従来、論文博士で学位を取得した先輩がほとんどである場合、なぜわざわざ博士課程に入学する必要があるのかという問いを、先輩が素朴に発する場合も少なくないようである。いずれにしろ、本人にとっても企業にとっても、大学院に入学する強い動機に欠けているのが現状である。この問題を根本的に解決するためには、日本の企業社会全体の流動性を、アメリカ並みに高めることが必要であろう。従来の年功序列の社会が続く限りは、社会人大学院の意義の認識も高まらないであろう。財界全体も、この問題は認識しており、何らかの改善を考えていきたいと思っているところである。今すぐに、アメリカ同様、学位取得によって給料を上げるような制度を導入することは容易でない。が、企業間の流動性が高まれば、自然にそのような方向に行くであろう。また、そうなりつつあると考える。」との認識が示されています。
1999年にそういう議論を行っていたというのは、なかなか示唆的ではないでしょうか。1990年代から今に至る日本の「失われた30年」を暗示していませんでしょうか。「今すぐに、アメリカ同様、学位取得によって給料を上げるような制度を導入することは容易でない」というご意見に対して、我々は、「なんとか、今すぐ、そうしてください」と申し上げるべきだったのかもしれません。先端学際工学専攻の成功につづいて、いろいろな大学が、社会人大学院生を積極的に受け入れるようになりましたが、残念ながら、当初めざしていたような、社会全体の変革からは、まだまだ程遠い状況だと言わざるをえないように思われます。
ここいらで、先端研らしく、また、新しい発想で、何か大胆なことを始めてみるのも良いのではないかと思います。守りにまわることなく攻めつづけられることを、期待いたします。

2001年度
橋本 毅彦
- 東京大学大学院総合文化研究科 教授
先端研在籍中の思い出
先端研に在籍したのは1996年から2006年までのこと、教養学部から移り、またそちらに戻り今在職最後の年を過ごしているところである。その間務めた専攻長としての仕事の思い出を一つ。入学式に博士課程の新入生に一言挨拶したが、その際に技術史のエピソードを一つ披露した。テレビの初期の開発に関わった日本の技術者で高柳健次郎という人物がいる。彼は技術学校の卒業に当たり、眼の前の課題ではなく将来を見据えた課題、しかも多くが関わる10年後ではなく、更にその先の20年後を目指して取り組んだ。そこで、当時の多くが研究するラジオではなく、画像を送信するテレビに挑戦することにしたというのである。今の時代20年後は少し遠すぎたかもしれない。すでに目の前の課題にセミプロとして取り組んでいる博士課程への入学生にはピンとこない話だったかもしれず、思い出すと半分申し訳ない気持ちである。
先端研在籍中には、専門とする科学技術史の研究テーマから先端研のルーツである航空研究所の歴史に関心をもち、まだ残されていた史料から多くのことを学ぶことができた。同僚としていらっしゃった多くの著名人の中の一人、立花隆さんも私と同様に航空研究所の歴史に関心をもち、学生とともに「先端研探検団」を立ち上げ、その歴史を探ってくれた。その立花さんに、遠くない将来の資源枯渇の問題と不安を問い尋ねたことがある。それに対し先生は「心配には及びません。大事なのは人を育てることです。」優秀な若い人々が出てくれば、少資源の日本も将来に到来する大きな問題もなんとか解決し困難な時代を乗り越えてくれるだろう、そのような回答だった。
これからも最先端を大胆に追い求めつつ、後進の着実な育成に取り組んでいってもらいたいと期待している。

2002年度
廣瀬 通孝
- 東京大学先端科学技術研究センター サービスVRプロジェクト プロジェクトリーダー
- 東京大学 名誉教授
先端技術30年周期説
先端学際工学専攻30周年おめでとうございます。
先端研でよく言われることは、「先端技術は10年一区切り」であるが、今回はそれよりもう少し長い技術のサイクルについて記してみたい。
小生は最近、先端技術30年周期説を唱えている。小生の専門はVR(バーチャルリアリティ)であるが、この技術が世の中の注目を集めたのが1989年、その30年後は2019年である。実はこのころ、VRの第2期ブームが始まっており、最近のメタバースブームへと至っている。
1989年は平成元年であるから、VRは平成と同い年と覚えればよい。考えてみれば、89年当時は講演するときも素材はスライドであり動画もビデオであった。ボストンバッグに10本近くのビデオテープを詰め込んで地方に講演に行ったのを覚えている。それが令和になると、ラップトップPCにすべてのプレゼン資料が詰め込まれるようになった。VRをはじめとする映像系のコンピュータ技術が社会に普及するまで、平成の30年間が必要であったということであろう。
技術が30年のサイクルを持つのは、ひとつには研究者のサイクルがそのくらいだからではないだろうか。研究者として独り立ちするのが30歳、定年が大体60歳ぐらいと見積もれば、研究者のサイクルは30年となる。この世代交代は不連続のジャンプという意味で好ましいことだと思っている。
生物も突然変異とその自然選択を繰り返しながら進化してきた。連続的な進歩と断続的進化こそが、最良の結果を生むと思われる。先端学際工学専攻も10年サイクル、30年サイクルを繰り返して、どんどん成長していくことだろう。ますます楽しみなことになってきた。

2007, 2008, 2011, 2013, 2015年度
馬場 靖憲
- 麗澤大学 学長補佐
同大国際総合研究機構 機構長
同大経済学部 特任教授 - 東京大学 名誉教授
組織革新により文系私学をケアの時代の主役に
日本の将来にはデータ駆動型社会への転回が不可欠であり、文系私学の工学系を加味した総合大学への変身が社会的責務となる。麗澤大学は令和6年度に工学部(データサイエンスとロボット工学)を新設する。文系に特化し安定に慣れた大学組織を先端技術の導入によってどのようにダイナミックに変革するか、そのための理念をどこに求めれば良いのか?
40年前、キャロル・ギリガンは、子供の成熟は、従来、自律性の獲得、権利主張の能力、抽象的な判断能力によって評価されたが、その指標とは別に、人間関係への文脈的理解、他者への配慮(ケア)も成熟のために重要とし、後者を見落とした理由として男性中心の発想のバイアスを指摘した。妻の命を救うために高価な薬を盗むしかない場合、ジェイクは命がお金より尊いとし価値の高低を根拠に数学的論理から盗みを正当化する。一方、エイミーは盗んだ夫が刑務所に送られるなら妻の病気は一層重くなると多角的に考え、答えを保留する。ギリガンはジェイクの思考法に対して、「もうひとつの声で」語られてきたケアの倫理(ethicofcare)―思いやりの道徳、配慮の倫理の存在に光をあてた。
他者への思いやりは市場価値がなく競争社会ではマイナスに作用するかもしれない。しかし、現在、社会全体が互いにケアを求めるケアの時代になってきたのは紛れもない事実である。ジェイクの思考法に慣れた自分がどのようにケアの倫理を身につける努力をするか、これは思いがけない難問である。ケアの倫理の再評価が本格化した今日、大学人の課題は、「もうひとつの声で」の価値をどう再発見するか、そして、それを先端科学技術の可能性とどう結びつけるか、真摯に取り組むことであろう。
新しい社会課題に先端学際工学専攻での経験をどう活かせるか、先端研諸氏の暖かい見守りに期待します!

2019, 2021年度
元橋 一之
- 東京大学大学院工学系研究科 教授
- 東京大学先端科学技術研究センター 教授
先端学際工学による画期的なイノベーションの社会実装
画期的なイノベーションはどのようにして生まれるのか?技術経営の分野では長年この問題に対して研究が行われてきており、いろいろなことが分かってきている。ただ、画期的に込められている「新規性」とイノベーションに込められている社会インパクトの間に根源的な対立があり、決定打が出ていない状況ともいえる。つまり、画期的であるためには、これまでにない新しいものである必要がある。ただし、人間行動には現状維持バイアスがあるので、新しいものは受け入れられない傾向がある。従って、営利目的の企業としては、このようなリスクの大きい投資に対して、どうしても躊躇してしまう傾向にある。
そこで重要となってくるのが、大学などの公的研究機関の役割である。特に多様な分野で先端的な研究者が集結する先端研の果たすべき役割は大きい。画期的なイノベーションにおけるもう一つのジレンマは「独創性」と「多様性」である。例えば特許情報を用いた分析によると、独創的な発明は研究チームが小さい場合(場合によっては単独発明)により多く見られるというものがある。研究チームが大きいと個々の研究者の独創的なアイディアが相殺されて最終的なアウトプットが丸くなってしまうからである。一方で、多くの画期的なイノベーションは異分野の組み合わせで実現するということも分かっている。「情報」+「バイオ」=バイオインフォマティクスという典型的事例の他、経営学の分野でも「情報」はもちろんのこと、「デザイン」との融合分野で産業応用を含めた進展が見られる。
つまり、個々の先端的な研究者がそれぞれ独創的な研究を行い、その一方で研究者間におけるルーズなつながり、異分野の創発によるセレンディピティが期待できる先端研は、画期的イノベーションを生むための理想的な環境にあるのではないかと思う。先端学際工学専攻は、先端研における研究とともに博士人材を社会に輩出する役割を担ってきたが、画期的なイノベーションを社会実装するために大きな役割を果たしてきた。「先端」と「融合」を両立できる人材育成に今後も期待し、貢献していきたい。