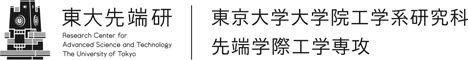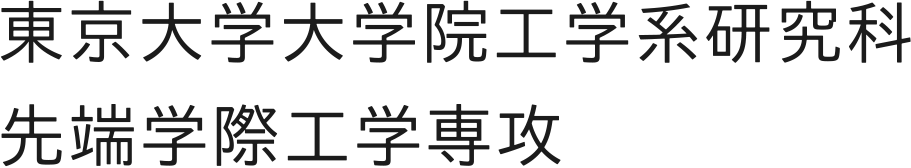- ホーム
- 専攻について
- 先端学際工学専攻 開設30周年
- 学位取得者インタビュー VOICE 1
学位取得者インタビュー VOICE 1

-
福島 智
東京大学先端科学技術研究センター
バリアフリー分野 教授- 【論文題目】
- 福島智における視覚・聴覚の喪失と「指点字」を用いたコミュニケーション再構築の過程に関する研究
- 【学位取得】
- 2008年5月
バリアフリー分野で教授を務める福島智氏は、18歳で全盲ろうとなってから、常に新たな道を切り開いてきた。1983年、盲ろう者として日本初の大学進学。都立大助手、金沢大助教授を経て、2001年、先端研に助教授として着任した。全盲ろう者として正規で常勤の大学教員になったのは、世界初とされる。2003年には米国TIME誌によって「アジアの英雄」の一人に選ばれた。「盲ろうになったときから漠然と『自分には何かすべきことがあるのでは』という予感がしていた」。45歳で博士号を取得して、たどり着いた問いとは?
生い立ちが映画化
駒場のキャンパスが満開のイチョウで黄色く染まった2022年11月上旬、春めいた題名の映画が各地で封切られた。「桜色の風が咲く」―。9歳で両目を失明し、18歳で両耳の聴力を失った福島氏と、支え続けてきた母・令子さんの実話をもとにしている。令子さんが発案した「指点字」という会話手段を使い、福島氏は他者とのコミュニケーションを回復させた。映画終盤、指点字が誕生した瞬間が描かれる。盲学校高等部2年の冬から急激な聴力の低下で、突然、無音漆黒の宇宙空間に放り出されたように感じていた福島氏。ある日、外出する時間が迫り、台所にいた母を急かす。点字を打つ道具も暇もない母は、ふと、思いついて息子の両手を取った。指を重ねて、点字のタイプライターのように軽く押す。「さ と し わ か る か」。不安と孤独の中にいた青年がにこっと笑う。「わかるで!」。暗闇に閉ざされていた世界に光が差した。福島氏が希望を持って大学に進学する姿で幕を閉じる。

- 学位記を授与される福島氏(左)
再びの孤独と再生
実際、全盲ろうになった後に郷里の神戸から東京の盲学校へ復学すると、級友たちは指で次々と話しかけ、温かく迎えてくれた。ただ、映画では描かれなかったが、復帰後から数か月間、福島氏は再び深い孤独を体験している。1対1なら指点字で会話ができても、相手が話しかけてくれないと、自分から会話の相手を探せない。誰かと話している最中に、第三者が加わって友人同士がやり取りを始めると、状況が把握できない。福島氏自身は以前と変わらず、声で発話し、外見上の変化もなかったため、周囲はその孤独になかなか気づけなかった。そんな中、全盲の先輩Mさんが指点字で「通訳」してくれたことがきっかけで、福島氏の世界は大きく広がる。通訳とは、直接、手に触れている人が、第三者の言い回しをそのまま伝えたり、周りの状況をラジオのスポーツ中継のように分かりやすく伝えたりすることだ。例えば、それまでの指点字だと、「I君は22日におうちに帰るんですって」と伝えられるところを、その先輩Mさんは「M:I君はいつおうちに帰るの? I:うーんとね、22日に帰ろうと思うんだけどね」と映画の台本のように打った。誰が発言したのかが明らかで、発言内容だけでなくニュアンスも正確に分かる。目の前が開けたような気がした。この「直接話法」は、今も指点字通訳の基本となり、福島氏と外部環境をつないでいる。自分が経験したこのコミュニケーションの喪失と再生の道のりを分析、考察したものが博士論文だ。
自己についての自己自身による研究
博士論文では、生まれてから19歳までの自分を「智」と位置づけ、「智」の言動や状況を振り返ってインタビューに答えたり、手記を残したりしている自分を「福島」、執筆している自分を「筆者」とした。参考資料は、幼稚園時代の絵日記、目の治療で入院中にクラスメートへ出したお礼の手紙、作文、歌や詩といった幼少期の創作物から、中高生時代の手記、母の日記、写真、聴力検査の記録など多岐にわたる。耳が聞こえた頃、落語や音楽をカセットテープに録音する際、自分の近況報告を吹き込む習慣があり、幸い神戸の自宅に900本近くのテープが残っていた。当時の自分をよく知る関係者たちにインタビューし、福島氏自身も改めてインタビューを受けた。
博士論文の執筆は、誰しも膨大なデータと作業量を要する。さらに、盲ろうであるが故に資料の整理や読み込みは、一層の時間とエネルギーが必要だった。点字では、流し読み、一目で情報をぱっとつかむといったことができない。自身の日記の原文は点字のため、一度、朗読・録音し、研究支援者が電子データに変換、それを福島氏がパソコンと点字ディスプレイなどを用いて読んだ。多くの支援者の協力があり、書き上げることができた。
伝えたかったこと
「コミュニケーションで本質的に問われていることは何か。言葉の文脈だけではなく、感覚の文脈がある。視覚と聴覚を奪われた盲ろう者にとって、この二つがともに重なることが必須の情報であると導き出した。オリジナルの思想を紡ぎだせたということが、博士論文を書いた意義かと思う」と振り返る。相手の表情や声の調子、しぐさなど非言語情報がないと、言葉の背景に隠れた意図は分からない。言葉だけでなく、「感覚的情報」を提供することは、盲ろう者の自立と社会参画にとって重要であり、例えばネット空間でのコミュニケーションを交わす現代の多くの人たちにも示唆的な知見であるとも論文で述べた。先端学際工学専攻で学ぶ学生には、「自分が心惹かれている問題に徹底的に食い付き、探求していく。良い意味でのしつこさと諦めの悪さを持ってほしい」と呼びかける。福島研究室では、これまで7人の学生を受け入れ、うち2人は視覚障害のある外国人留学生。1人は執筆中で、残り全員が博士号を取得した。いずれも「こういう問題があるので、解決したいなど目的意識がはっきりしている人、自分が興味を持っていることについて問わずにはいられない人」だったという。

- 2015年1月、先端学際工学特別講義で講演する福島氏(右)
これから
博士論文では深く整理できなかったことがある。これまで出会った人の中には、難病を患った結果、視覚、聴覚を失った人もいる。「博士論文の後にたどり着いた大きな問いが、人が生きる上で過酷な状況に置かれたときに何ができるのかということ」。「多重複障害盲ろう者」の事例を分析することで、何が彼ら・彼女らを励まし、打ちのめしているのか。その人たちの人生を豊かにするにはどうしたらよいのか。その知見は、視覚、聴覚の障害のみならず、精神障害や知的障害のある人への支援についても、新たな示唆を提供できるのではないか。「これから突き詰めていきたいテーマです」。